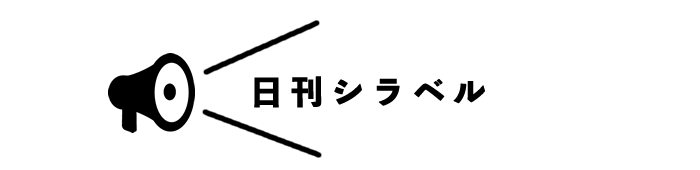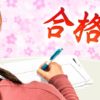幼稚園の送迎を苦痛に感じている人に。対処法をご紹介します!
2017.9.7

人見知りのママやパパにとっては、幼稚園の送迎が苦痛に感じてしまうかもしれません。
そんなママやパパは、送迎時の何に苦痛を感じているのでしょう!
何に悩んでいるかや、解決法をご紹介いたします。周りを見たら同じ事に悩んでいる人もいるのかもしれませんね!
スポンサーリンク
こんな記事もよく読まれています
-

-
小学校の学級崩壊事例・・・それはこんなところから始まってる!
親からすれば小学生なんてまだまだ子供で可愛いもの。ですがたびたび学級崩壊などの噂さを耳にすることがあ...
-

-
高校の部活が苦痛で辞めたい・・・部活に行きたくない時の対処法
高校に入学して部活にも入り、楽しい高校生活を満喫するはずだったのに・・・ 部活に行きたくないと...
-

-
学校のチャイムがならない時代に!チャイムがならない理由とは!
学校生活で時間を教えてくれるものと言えば「チャイム」ですよね!大人になってからもチャイムの音を聞くと...
スポンサーリンク
この記事の概要
幼稚園の送迎を苦痛に感じているママの体験談をご紹介
幼稚園のママ友問題に悩むママたちにとって「本当に毎日ウンザリ。送迎が辛い」と声高に言われるのが幼稚園バス。
毎日、しかも行きと帰りの2回、ほかのママたちと会わざるをえない園バスの送迎は人付き合いが苦手な人にとって大きなストレスになります。
実際にトラブルは起きているのでしょうか?ママたちの体験談を集めてみました。
○下の子を置いていなくなるママ友にウンザリ
ある日、いつも通りにバス停に行くと「これから病院の受付をしてきたいから、下の子見ててもらえる?」と言われました。もうすぐバスが来る時間だったし、いつも込んでいる病院だったので受付だけならとOKしてしまったのが間違いでした。
その子はおとなしい子だし、問題なく園バスが来るまで、うちの下の子と一緒に待てたのですが、その日から「今日は下の子の調子が悪くて」など色々な理由をつけて子供を私に預けていなくなるようになってしまいました。
一緒にバスを待つだけですが、あまりにもアテにされているとモヤモヤします。
○帰り際の「○君の家に行きたい~」が毎日ストレス
子供たちが園バスを降りると「今日ヒマなんだよね~」と言うママ友。示し合わせたようにそのママの子供が「今日、○くん家で遊びたい!」と騒ぎます。
最初のころは自宅に招くこともあったのですが、夕方になっても帰ってくれずマナーが悪いので最近は断っていますが、なかなか諦めてくれないので困っています。
幼稚園の送迎の苦痛のタネであるママ友との付き合い方
子供が小学校に入れば、親同士が顔を合わせるのは運動会や発表会や参観日ぐらいに激減します。
なので、顔見知りのママとでも、スーパーなどでたまに見かけてもひと言挨拶をする程度の付き合いになります。幼稚園時代、あんなに頑張って付き合っていたのが、一体何だったんだと思うくらいアッサリ。
しかし、運悪くママ友との集まりが大好きなグループに所属してしまうと、子供が小学校に入っても、「ランチしよう」「お茶しよう」などと、お誘いが続きます。
それが楽しいなら問題ありませんが、楽しくない場合は大変です。しかもお金もかかります。もしもこの付き合いを負担に思うのであれば、好きでもないママさんたちとは距離をおいて付き合ったほうが賢明です。
距離をおいて付き合う具体的な方法は、丁寧語や敬語を使うのがオススメです。最近のママさんたちは、年齢なんて気にせずフレンドリーに話をする人が多いです。
そういうタイプのママさんたちは、ママ友で集まるのが好きな可能性がとても高いです。
ですので、そういうタイプのママさんとも自然に距離をあけるために、敬語をきちんと使うようにすると効果的です。自分たちとはタイプが違うと感じてもらえます。
人見知りで幼稚園の送迎時のおしゃべりが苦痛。一体どうしたら?
私は昔から人見知りで、人付き合いも苦手なほうです。そのせいもあって、もう幼稚園も3年目になりますが、園に行った時に話せる人は数えるほどです。
他にも人付き合いが苦手な人は結構いると思います。もしも毎日の園の送迎が苦痛だと感じているのであれば、無理をして他のママさんたちのの輪に入ろうとしなくても良いのは?
仲良くしたい人がいて、輪に入りたいと思うのであれば頑張る必要があるかもしれませんし、頑張れるのかもしれません。
だけど、苦手に思っているのであれば、無理をするのはお勧めしません。もっと自然体でOKです。園に通ってるのは、あなたではなくお子さんです。
あなたが他のお母さんたちとのお付き合いが苦手だからと言って、お子さんが意地悪をされたり仲間はずれにされることはないのですよね?
園に行く目的は「他のママさんたちとおしゃべりに行く」のではなく、「お子さんを迎えにいく」のです。シンプルに考えるとずっと気持ちも楽になると思います。
幼稚園の送迎があまりにも苦痛な場合の対処法とは
幼稚園の送迎があまりにも苦痛で、気にしない、割り切るだけでは済まず大きなストレスになってしまっている場合は、もしかしたら心療内科の出番かもしれません。
バス待ちの時間のお誘いが苦痛なら、仕事へ出ることもひとつの方法ですが、実家の親を理由にするのも手です。入院しているとか、介護まで行かなくとも手伝ってほしいと頼まれていることがあるとか、いろいろ理由もありそうですよね。
幼稚園や保育園生活は結構長いものですし、私は仕事もしたいと思っているので、きちんと自分のペースで過ごしたいと思っています。
その結果、ある程度周囲とは距離をとって過ごしていますが、先生とは毎日お話していますし、他のママさんに話かけられれば、普通にお話ししています。
ですが、うちは年中からの入園なので、年少から通園しているママたちはすでに仲がいいように見えます。なので無理に入っていかず、挨拶も無理ない程度にしています。
仲の良いママを作ろうと気合をいれなくても、その時その時で、聞きたいことがあれば近くの人に話しかけてみれば、欲しい情報は得られますし、肩に力が入っているよりもずいぶん気が楽だと思いますよ。
幼稚園の送迎が苦痛になった理由はこんな考え方のせいです!
子供の送迎時の様子を、思い浮かべてください。ポツンと一人でいるのは、きっとあなただけではないと思います。
うちの幼稚園も、よく見てみると10分前に迎えに来ずに、遅れて来る人たちがたくさんいます。中には車で待機していて、時間になるとさっと来て、さっと帰る人が意外と多いです。
今までの私には、おしゃべり大好きなにぎやかママたちしか目に入ってなかったのかもしれません。
でも、周りをきちんと見てみたら、私のような雑談苦手なお仲間が意外といるって気づきました。そして、私の苦痛の最大の理由は、自分でも思っていた以上に「子供を守らなければ」という意識が強かったようです。
子供を守ることこそが子育てで、子供を守れない親は子育てもきちんとできないダメ親だと思い込み、人間関係で悩んでいる自分はダメ人間だと焦っていたようです。
ずばり、私のママ友づきあいが子供の人付き合いスキルにそのまま反映されると勘違いしていたので、私がひとりポツンとしててはダメだと自己嫌悪に陥り、身動きが取れなくなっていたようです。そんなことはないので、自然体で過ごしましょうね。
- 学校と教育